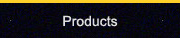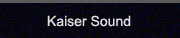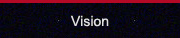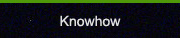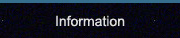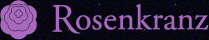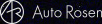�g�b�v��������X�s�[�J�[��Cardinal�V���[�Y�t�������W�X�s�[�J�[�ɂ��Ă̏�������C�i�[�m�[�c�i����ꂢ�q���猩���������j
���C�i�[�m�[�c�i����ꂢ�q���猩���������j
|
|
|
|
�@����J�������J�[�f�B�i���X�s�J�[�uThe Maestro�v�̉��̍ŏI�m�F�̒i�K�Ń{�[�J������F�X�ƒ����Ă������ł����B�������́uCaptain of the ship�v���Ȃ���A�ő��ɓǂ܂Ȃ����C�i�[�m�[�c�ɖڂ𗎂Ƃ��܂����B
�@�`�����炻�̕��ʂɓB�t���ɂ������܂����B�N���������̂����������������ɓr���Łu���͏�������v�Əo�Ă��܂����B�����Œj�̐[�w�S��������Ȃɋ��ݎ���̂��Ƌ����܂����B�ǂނ̂𒆒f���y�[�W���߂���Ɠ���ꂢ�q����ł����B�������ł��B
�@�N���ɓǂ�ŗ~�����I
�@���̉��l����l�Ԋώ@�͂��E�E�E
�@�����v�����̂ŁA�������菑���ʂ��Ă݂܂���
|
|
|
�@���{�l�ɂ́A���������D���Ƃ����l�ƁA�����Ƃ����l�̓��ނ�����B�����Ȃ�Ēm��Ȃ��Ƃ����l�́A�قƂ�ǒʏ�̎s�������𑗂��Ă��Ȃ��l������A���̍ۂ��܂�W�Ȃ��B
�@�D�����A�Ƃ����l�ɂ́A�Ȃ��H�ƕ����K�v�͂Ȃ��B�F�A�u����Ȃ��Ȃ��ɂȂ肽���āA����Ȃ��Ȃ��ɂȂ�Ȃ��āv�A�������g�̓��ɁA�����ƍ��̐����ȗD�����Ɛ������܂��A�M�����߂Ă���l���������炾�B
�@�������A�Ƃ����l�̔����́A����Ɋr�ׂ�Ɛ獷���ʂ̗l����悷��B�u�Â��v�u���������܂����v�u���N�U���ۂ��v�u�\�͓I���v�u�e�\�Ȋ���������v�u���݂��悤�ȉ̂������C���v�u�q�Q���s�������炵���v�ȂǂȂǁB
�@���̎��͂ɂ��A���`�����h�͑�R����B�l�C�̂���X�[�p�[�E�X�^�[�قǁA���̒��̔����͓�����̂�����A�g�т����ɓ{��قǂ̂��Ƃł͂Ȃ��B
�@�ł��A�����Ȑl�ɁA���̗��R��[�������˂Ă����ƁA���ǂ́u���܂�A�����ƕ��������Ƃ���������ǂ�����Ȃ��v�Ƃ����Ƃ���ɍs�����B
�@�D���ł��Ȃ����̂��A�M�S��CD���Ă܂ŕ����͂��͂Ȃ��̂�����A�u�����v�̍����́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�C���[�W�ƁA����Ȏv�����݂ƁA����Ɋ�Â��Ă���Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@�������g�̎コ��A�ӂ����Ȃ��ɖڂ������邱�Ƃ��Ȃ��A����𗬂����܂܂ɐ����Ă���l�ɂƂ��ẮA���̂悤�Ȑl�̓E�U�������f��̂�������Ȃ��B
�@�W�����A�i�����̂�������ɗ����ėx���Ă��鏗�̎q�ƁA�A���}�[�j���̃X�[�c�𒅂āA���̏�������������悤�Ɍ��グ�Ă���j�����ƁA���̎p�Ɏ��X�ɃJ������������W���[�i���X�g�قǁA���̉̐���������Ȃ����̂͂Ȃ����낤����E�E�E�E�E�E�ƍl���������ŁA�v�킸�N�X�b�Ə��Ă��܂��B
�@�����̌��t�ŁA����قǂ̃X�P�[���̑傫�ȉ̂��A����قǂ̐������ʼn̂��Ă����A�[�e�B�X�g�́A���Ȃ��Ƃ����̓��{�ɂ́A����u���đ��ɂ��Ȃ��B
�@�O���ɂ͂���̂��A�ƕ����ꂽ��A�u�����˂��A�u���[�X�E�X�v�����O�X�e�B�[���Ƃ��A�X�e�B���O�Ƃ��A�R���[�E�n�[�g�Ƃ��E�E�E�E�E�E�v�ƁA���̍D���Ȑl�B�̖��O������オ�邯�ǁA�X�P�[���Ƃ����_�ɂȂ�ƁA����́u�K���W�X�v�������Ă��镨�ɑ����ł��o����l�́A������Ƃ��Ȃ���������Ȃ��A�Ǝv���B�i�ƊE����̔��_������A���Ђǂ����j
�@�ʂ����āuJAPAN�v���z����A���o���͏o����̂��낤���A�Ǝv���ė�������Ǔ͂���ꂽ�����āA�������B2�x�A3�x�A�������тɁA�[�������������ċ����Ă��܂����B�����܂Ŏ����̌��E�Ƀi�C�t��˂����āA������Ƃ�����Ƃɐ^���ɂȂ�Ȃ������āA�����ɂȂ�܂����z�̌b�݂͂���̂ɁB
�@36�ˁA2���̕��A�l�̂��邳��������Ɠ����ɁA���̐l�̒ɂ݂������Ă���A�ނ��������N���ł�����B�����̂̂悤�ɁA�X�g���[�g�ɂ́A���_�I�ɂ����̓I�ɂ��{��Ȃ��B�������ӂ�̈�ł����Ă�肽���Ȃ邵�A�����݂ȍK���Ƀh�b�v���͂܂��ĕ�炷���Ƃ����đI�ׂ�̂�---�B
�@���Ă݂�A����L�͎��������l�������ꂸ�A�l���ɓ��ݎU�炳��Ď���ł��܂������A���̐l�����̐l���A�|�b�e���Ƒ��������N�ɂȂ��āA�V�[������͏����čs���Ă��܂����B
�@����Ȃ̂ɍ��͍����A�������������ɂȂ肽���āA�������������������䂭�āA���M�ƁA�s���ƁA�v���C�h�ƁA�R���v���b�N�X�ƁA��ƁA�~�]�ƁA���S�ƁA��S�̂͂��܂ŁA�Y�^�{���ɂȂ�Ȃ���������Ɋ��݂��A����ɒ܂𗧂āA�����ɉ���ނ��āA�㒎�̎�������w���ł������Ƃ���B���̎���A�����܂Œj���ۂ�������A�����Â炢���낤�ƁA������ւ����Ȃ��B
�@�j�̒��̏������A���̒��̒j�����̊J���Ȃ�Ă��Ƃɋ��������鎄�́A�u����̒d��ŁA�u�����Ђ�����O�֑O�i�����Ƃ���낪�����j�����Ȃ�Ă��̂́A���Y�ƊJ���Ɍ���������������A�n���̂��߂ɂȂ�܂���B���ꂩ��͍Đ��̎���A�������ƕꐫ�̎���ł��B������j�̐l���A�����̒��̏��������A�����Ɖ�����ĉ������v�Ȃ�ČĂт������肵�Ă���B
�@���̂��Ƃ́A���̃t�@���ł��邱�ƂƖ�������̂��낤���B
�@�m���ɁA�u�����ƑK���~�����B�������������A�ł������Ƃ��~�����v�ȂǂƁA�悶�ꂽ���ŋ����ƁA�I�[�b�ƁA�Ȃ�Ďv������ǁA�������߂Ă��镨�́A�����Ƃ����ƃf�J���Ƃ������ƂɁA�₪�ċC�Â������B
�@�~�����A�~�����A�~�����̃J�^�}�����A��O�̋S�Ɖ����āA�����āA�����āA�����Ă��ǂ�����Ƃ��Ă����́A�Ȃ�ƌ���Ȃ����߂̐��E���Ɖ����Ă��܂����炾�B
�@�u����Ȃ��Ȃ��ɂȂ肽���āA����Ȃ��Ȃ��ɂȂ�Ȃ��āv�ƁA�����ܖڂŊ���������ɂ��镨�́A�Ђ�����ꐫ�ł���A���܂˂����A�j�������A�S�Ă̗~�]���������A�R�Y�~�b�N�ș�䶗����E�ɔ��ޖ������A���ӕ�F�̎��߂̐S�Ȃ̂�����B
�@������A����Ȏ�������ӎ������������ł��鎄�Ƃ��ẮA�u�����Ă��邩��A�S�z���Ȃ��Łv�Ƃ��A�u�閾���O�̌��������āA���O�ɉ�ɍs�����v���Ƃ�������ƁA�|���|���܂����ڂ��ĕ����Ȃ�����A�u��k����Ȃ����B����������āA�҂��Ă���͂����Ȃ��B�������āA���Ƃ����D�̃L���b�v�e���Ȃ���v�ƁA�����߂��ʂ̂ЂƂ��������Ȃ�̂�����ǁA���̊�̏X�����A�����ɒp���Ă��܂��B
�@�ꐫ�̂Ȃ��Ƃ���ɂ́A�l�ނ̖����͂��납�A�n���̖������������̂��ƁA���͌����Ă�����̂ˁB���̈ꌩ�U���I�Ȓj�����̗��ɂЂ��ގ����̐S�̗D�����ɑł����̂́A�u���[�X�E�X�v�����O�X�e�B�[���̉̂����Ɠ������ƁA���͎v���Ă���B
�@
�@�����������m�����̂́A���q�ƃu���[�X��ʂ��Ă������̂�����ǁA���N8���̃f�g���C�g�ł̃u���[�X�̌��������ɍs�������A���{�Ԓ@���̖{���n�̃X�e�[�W�ŁA�Ȃ�ƃu���[�X��2���l�̋q�ȂɌ������āuMY FRIEND FROM JAPAN,TUYOSHI NAGABUCHI!!�v�Ƌ���ł��ꂽ�̂������B
�@�����������Ȃ��A����́B�v�킸�W�[���Ɨ܂����ݏグ�ė��āA�������B�����āA�u�����M�����p�ꌗ�ɐ��܂�Ă�����A�u���[�X�ɂȂ��Ă��������m��Ȃ�����v�Ǝ������������̍��̌��t���A�܂����������B�u�Ⴄ��A���삳��B����ς萢�E��ɂ��Ă���z�̓f�J�C��v�ƁB���ꂪ65,000�l�̃h�[���̃`�P�b�g���A41���Ŕ����������̒j�̌��t���������ƂɁA���͂܂��������Ă��܂����̂������B
�@����A�̂������烍�C�E�r�^���̃_�E���E�g�D�E�A�[�X�ȃu���[�X�E�s�A�m���������ăA���o�����n�������A�]�N�]�N�ƒ������������̂́A���̃f�g���C�g�̖���v���o��������ł��������B
�@�u���[�X��E�E�X�g���[�g�E�o���h�ɂ����āA1974�N����I�n�u���[�X�ƍs�������ɂ��ė����L�[�{�[�h�t�҂ł���A�A�����W���[�Ƃ��Ă��A�o���h���[�_�[�Ƃ��Ă��ł��d�v�Ȑl�����A���̐l�ł���B�s�[�^�[�E�K�u���G����_�C�A�[�E�X�g���C�c�A�f���C�b�h�B�{�E�C�Ȃǂ̃r�b�O�E�A�[�e�B�X�g�̃��R�[�f�B���O�ɎQ�����Ă��鑼�A�ŋ߂ł̓p�e�B�[�E�X�}�C�X�̋v�X�̃q�b�g�A���o�����v���f���[�X���Ęb����Ă�ł���B
�@�������Ƃ́uJAPAN�v���炢�̕t������������A�t�@���̊F����̕����悭�����m���낤�B������������A�O�C�ƈꏏ�Ɋ�𑵂��Ă����M�^�[�̃e�B���E�s�A�[�X�A�x�[�X�̃W�����E�s�A�[�X�A����Ƀh�����X�̃P�j�[�E�A�[�m�t�̖��O��������B
�@�W�����ƃe�B���́A���܂�ɂ��L����L�EA�̃X�^�W�I�~���[�W�V�����ŁA�{���W�����B��x�����_�E�J�[���C���A�V�F�[���A�e�����X�E�g�����g�E�_�[�r�[�̐V��ȂǁA������Ȃ��b��̃A���o���ɎQ�����Ă��邵�A�h�����X�̃P�j�[�E�A�[�m�t���A�W�����E�i���N�[�K�[�j�E�������L�����v�̃A���o���ɑS�ʓI�ɎQ�����Ă��鐦�r���B
�@�������A����Ƃ������A��Ƃ������A���̎O�l�������������āA�J�i�_����̋C���l�ԂŁA���������Ă�܂Ȃ��R���[�E�n�[�g�́uBANG!�v��uATTITUDE&VIRTUE�v�Ƃ������A���o���ɎQ�����Ă��邱�Ƃ��A�s�v�c�ł��܂�Ȃ��B�u���A���Ȃ킿�l�Ȃ�v�ƍl����A���y����������l�X���A�����~���[�W�V������]�ނ͓̂��R�̂��ƂȂ̂����m��Ȃ������---�B
�@�����Ă܂��A�A�����J�암���������ׂ��~���[�W�b�N�E�t���[�N�ŁA�G�����B�X�E�v���X���[�ɓV�[�����Ƃ����g���E�y�e�B�[�m�o���h�A�U�E�n�[�g�u���C�J�[�Y�̃����o�[�ł���A�����W���[�A�����ς�_�R�̐l�C�~���[�W�V�����ł���L�[�{�[�h�̃x�������g�E�e���`���A���C�E�r�^�����Q�����Ă��Ȃ��Ȃł́A���C�ɑ����ăL�[�{�[�h��e���Ă���B
�@�u�����̕��ɐg���܂����v��u�K���W�X�v�̂悤�ȁA�ǂ����̂ǂ��ŃA�R�[�X�e�B�b�N�ȋȂɁA�h�m���@����h�A�[�Y�A�J�[���E�{�m�t�A�E�H�[�����E�W���H���A�����ĒN�����W�F�C���X�E�e�C���[�Ŗ���y�������C�ݐ���̃x�[�X�t�ҁA���[�����h�E�X�N���[���Q�����Ă��邠��������������B
�@�~���h�����̍��A�ǂ�Ȃɍ��ȃ~���[�W�V���������āA�ꎞ�ԂȂ�ڂ̐��E���낤���A�ƁA��߂��ڂ����Č���l�����邩���m��Ȃ�����ǁA����ł͉����Ⴄ�B���̃A���o���ŕ������Z�b�V�����́A�����Ȃ�u�l�ԂɂȂ�Ă��v�ŕ������e���V�����̍����Ȃ��Ă���ƁA����͂��Ȃ蒚�X���~�Ƃ�荇�������낤�ȁA�Ƒz�������̂��B
�@�u�����͈Ⴄ�v�ƒ������o���Ă݂��Ƃ���ŁA�t�H�[�N�����ă��b�N�����āA���ɂ�������ǃA�����J�������ė������̂��B���������C�E�r�^���ɂ��Ă��A�x�������g�E�����`�ɂ��Ă��A�u���̓f�B������u���[�X�Ƃ���Ă�����v�ƁA�ЂƂ��Ƃō����̂Ă邱�Ƃ��o����l�B�Ȃ̂�����B
�@���E���A���j��ɂ��ė����A���Ƃ����̂́A�����f�J���B�����ǂ��m���āA�K�b�v���Ǝl�ɑg��ł́A�����炭�͌��ɏo���Ă����Ȃ��قǂ̓��������������Ƃ��Ǝv���B
�@���̌��ʁA�T�E���h�Ƃ��Ă����e�Ƃ��Ă��{���ɑf���炵���A���o�����o���オ�������ƂɁA���͐S����h�ӂ�\����B
�@�����͐l���ꂼ��A�Ȃ��ꂼ��ɈႤ���Ƃ��Ǝv�����A�Ȃ�Ƃ����Ă������̂́A�^�C�g���\���O�́uCaptain of the ship�v�Ɓu�K���W�X�v��2�Ȃ��B
�@�@���Ƃ����̂Ƃ͑S���W�Ȃ��A���̉F���͎����������镨���ׂĂɑ��āA�u��������I�v�Ƃ����w�߂��o���Ă���E�E�E�E�E�E�Ɖ��߂��A�����Ɏ��߂������߂��܂߂āA�����̖@���Ɨ։�݁A�������Y�C���h�𗷂��Đ[��������Ƃ��낪����A���Ɋ����i�����ڂƂ��j�Ƃ�����`�x�b�g�̐��_�I�w���҂ł���A�m�[�x�����a��҂ł���_���C�E�_�}14�����Ȃ����B
�@���ꂪ�ЂƂ��ƁA�u����Ă��Ȃ�������v�Ƃ����B�u�I���A���C�ɓ��肽����������A���������A�Ǝv���ċA���ė����v�Ƃ����B���̎��́A�ǂ��~�߂Ă����̂����v�肩�˂Đ�債������ǁA�₪�ē͂���ꂽ�u�K���W�X�v���āA�����������̂��ƁA���̋C�������ɂ��قǗǂ��������̂������B
�@�C���h�̗��́A����ɂ��Ȃ��̐S��`�����݁A���Ȃ��̑z���i�͂���j�ɂ�����B�f���炵���Ɗ������āA�܂��������Ȃ邩�A������x�Ƒ��������Ȃ����̂ǂ��炩���Ƃ����邯��ǁA�����ɂ͂���ɍׂ����S��̂��߂�������B
�@���͎����̗��s���ɁA�C���f�B�[�E�W���[���Y�̂悤�ȊX�̕��i��A�^�W�E�}�n�[���̕����y�Y���ƈꏏ�ɕ��荞�݁A�����r�����邱�ƂŎ����̂�܂������������A�_���C�E���}�@���Ƃ����u�����h�i�ɉ���Ƃ��������ŁA�~�[�n�[�̂悤�Ɋ��ŋA���ė�������ǁA���̐S�̊��ɂ́A����ȊG�t���̂悤�ȕ��i���A�u�����h�i���A�������荞�ޗ]�n�͖��������̂��Ǝv���B
�@����ȍ��̐������Ɛ��������A�����ăf���P�[�g�ł��邪�䂦�́h�Ƃ�h���A�l�͎��Ƃ��ė����ł����ɑ��ނ̂��낤�B
�@���������B��������B�����n��A�����Y�ށB���̃v���Z�X�ŁA�������t�@�������܂߂āA�|�\�E�̓K�^�K�^�Ɠ����A�\���\���Ƒ����B�ł��A����ȃv���Z�X�́A�����ǂ��ł��������ƂȂƁA���̐��ݏo���ꂽ���ʂɁA���͎����̍��������悤�Ǝv���B�����Ă����A�\�b�ƐS�z���Ȃ���A���̏����������B
�@������A���͂��Ȃ��̕�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�t�@���Ȃ�Ă��傹��́A�ǂ��܂ōs���Ă����ӔC�Ȃ��̂��Ǝ��F���Ă����邯��ǁA�ł��m���ɁA���Ȃ��̑z���A���Ȃ��̗D�����A���Ȃ��̐����A���Ȃ킿���Ȃ��̖��́A���t�ƃG�l���M�[�̂����тƂȂ��āA����Ǝ������̍����������߁A������w�j���тƂȂ�A�����ɗ����������������̔w����@���āA�͂��܂��Ă����̂�B
�@�����ȃA���o�������肪�Ƃ��B
�@�ꂵ����Ƃ������Ǝv���B
�@
�@�����炱���A���̐V���������A�������ė܂����ڂ��Ȃ��狹�ɕ����āA����Ԃ�����Ԃ��A�H�ׂ�悤�ɁA�ۂݍ��ނ悤�ɁA�F��z���ŕ����Ă���B���������Ă��邳�����낤���ǁA�g�̂ɂ����͋C�����ĂˁB�����ɂȂ��āA���[�q�����������Ȃ��łˁB
�@1993�N9��7���@With Love �@����ꂢ�q
|
|
|
|
|
|
���@Back�@�@�@�@�@Next�@�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |